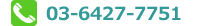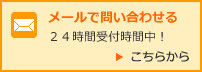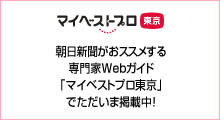TOP > メンタルヘルス対策 > 復職時の対応はどうしたらいいですか?
復職時の対応はどうしたらいいですか?
復職時の対応
うつ病など精神的な病気にかかってしまった方にとって復職がうまくいくかどうかが再発するかしないかに大きく影響してきます。
人によって対応を変えざるを得ない部分ももちろんありますが、基本的な会社としてのスタンス、会社として「できることとできないこと」をはっきりしておくことが重要と考えます。
ズルズルと腫れ物に触るように言われるがままの対応をしてしまうことで、周囲の社員への負担が増えたり、摩擦がうまれることにもつながる懸念があります。
少し冷たいかもしれませんが、会社と労働者はは「働いてその対価を得る」契約を結んでいることを双方がしっかりと再確認することも必要だと思います。
そのためにも、基本となる「職場復職プログラム」を策定しておくことをお勧めします。
職場復職プログラム策定のおよび復帰の際のポイント
どの状態まで回復したら復職を認めるのか
⇒これは会社が独自に決めていくことが可能です。
大きな会社であれば簡単な業務の部署があったりもするでしょうから、それがこな
せるならば良しとすることも可能です。
しかし、労働契約ですから、原則としてフルタイムで働くことができる程度(残業な
し)に回復していることが必要であると考えます。
主治医によっては仕事がどんなものかを考慮せずに復職可との診断書を書いて
くる場合が あり ますが、職場では労働できることが前提ですので半日であればと
いうような但し書きがあるよ うな場合は復職できる状態かどうかを慎重に判断する
必要がある段階であることが多いと思われます。
本当には回復していないけれど、休職期間満了がもうすぐだから、家族が働い
てほしいと言っているからなどの理由で、復職を願い出てくる人もいます。確かに社
員としての地位が危ぶまれたりしているのでお気持はわかりますが、無理をして復
職を果たしたとしても、あっという間にまた元のような辛い状態に逆戻りすることに
も繋がります。まずはあせらずじっくり治療に専念ていただく方が第一だと考えま
す。
あるいは最初の2、3カ月程度は短時間勤務を認める会社もあります。
ただし、この場合、復職として勤務してもらう場合はいいのですが、復職前の復職が
できるかどうかを見極めるためのものなどの場合、給与はどうするのか、労災
は・・・など問題があります。
安易にリハビリ勤務を導入することは避けましょう。
入れるのであれば、きちんと書面において何をしてもらうのか、給与は支払うのか、
「休職中」なのか「復帰後」なのか、労働が伴わない場合には労災保険の対象外とな
ることも十分ありますので、民間の保険に加入するなど取り決めを行うことが重要です。
復職を認める際の判断は何をもって誰がするのか
⇒1.主治医の診断書。
これは実際復帰できる状態かそうでないかに関わらず患者である労働者の
復職したいとの意向に応じる形で書かれたものがありますので、
うのみにするのは危険です。
2.産業医 あるいは お願いしている専門医の意見書、診断書
主治医とは別の専門家の客観的な診断が必要ですので、社員に受診してもらい
診断書等を貰いましょう。応じない者もいる場合がありますので、会社が命令す
る事が必要になることがあります。ために就業規則にこの旨記載しておく必要が
あります。就業規則も見直してください。
3.上記1.2をもって会社が判断します。あくまで労働者自身や主治医、産業医
等が判断するのではありません。会社内で復職判定委員会などを開いて最
終的には意思決定者が判断してください。
復職に際しリハビリ出勤をさせるのか
リハビリ出勤とは何か?
⇒ リハビリ出勤という言葉がありますが、ただ来るだけのものか労働させるかで
扱いが変わります。(お金が払われるのか、労災が適用されるか等)休職中で
あれば労災が適用されず、通勤災害などが発生する恐れもあることから、この
場合民間の保険に加入するなどの対応も必要となります。
会社は労働の場であって治療の場ではありませんから、原則フルタイムの時
間働けることが必要となると思いますので、私は原則としてリハビリ出勤はお勧
めしていません。
どうしてもというのであれば、最初の2週間程度は2時間くらい所定労働時間
を短くする、次に1時間くらい短くし、復職1~2ヶ月後くらいにはフルタイム残
業なしで働けるくらいを目指してはいかがでしょうか。長くても3か月位でしょう。
なお、時間が短くなったところの給与はその分不支給とするのが妥当です。
どの職場に復職させるのか
⇒ 原則 元の職場への復帰です。
新しい職場に戻すと、その新しい仕事に適用していくこともストレスになり
ますので、慣れている仕事に戻すのが原則です。
しかし、パワハラ・セクハラがあったことが原因であるような場合は別な
部署へ異動させるなどの対応が必要となってきます。
この場合でも、休職した社員を異動させるのか、加害者とされた人を異動
させるのかも検討しなければなりません。
本人が「この仕事だったから鬱になった、他の部署に異動したい」等といって
くることもあります。この場合どう対応するかは会社の考え方次第になります。
例えば、
・本人が望んでもパワハラなどの不都合があった場合でない限り、原職に復帰
・「他なら能力が発揮できる」と言っている社員の言葉を聞いて、別の部署へ異
動させる。ただしもしほかの部署でもダメだった場合の再異動は認めない
ここで重要なことは「会社の取り決めに従って」行うことです。
復職してくる社員によって対応を変えることは好ましくありません。
「前に復帰した○○さんにはこういう対応をしていたのに、私の場合には
同じ対応はしてもらえないのですか?」というようなことにもつながり
かねません。あるいは退職して貰いたいとひそかに会社が思っていたと
したならば、その対応の違いはその後訴訟にもつながりかねません。
復職する職場の人へどう説明し、どのように接していくのか
⇒ 復職する本人へ説明をし、まだ残業は無理であること、通院や服薬が必要であ
ることなど、フォローを必要とすることなどについての話をする必要があると思い
ます。どうしても本人が周りに話すことに難色を示すような場合は、フォローが受
けられないことなどを説明し、話すことに同意してもらえるようにしていきましょ
う。
なお、職場の人には特別扱いや腫れ物に触るように接するのではなく他の人
と同じように接するように伝えてください。 当人の言動一つにまで配慮を求めて
の復帰だとしたら、それは復帰できる状態とは言えないと考えられます。
職場は「働くところ」であってリハビリ施設や医療施設ではありません。
治療が必要なのであれば復帰は認めない方が双方にとって有益と考えます。
普通に接して大丈夫なレベルを復帰基準にするということも検討してください。
最近は、「休職していた人に戻ってきてほしくない」「あの人が戻ってくるなら私は
辞める」という社員がいるケースの相談を受けることが増えています。
休む前の職場の雰囲気というものが想像できます。どちらに問題があるかは
ケースバイケースですが、復職する社員を受け入れる部署内での事前の話し合
いや、物の捉え方、見方などについて研修なども必要な場合があります。
休んだ本人についても、単なる薬の治療だけでなく人間関係やモノの見方考え
方を変える「認知療法」などが必要と思えるケースもあります。働く場の会社として
どこを強く求め、どこは配慮していくのか見極めていくことがより求められていま
す。
復職してからのフォローをどうするのか
⇒ 産業医がいる職場であれば産業医が、いない場合は上司や人事が、最初は1週
間に1度程度、その後2週間に一度くらいのペースで面談し問題がないか、薬は飲
んでいるか、きちんと眠れているか等を聞いてもらうといいでしょう。
問題があることがわかったら早急に対策をうってください。再発するとさらに
治りにくくなってしまいます。
産業医の先生がいない事業場では、上司あるいは人事が定期的に面談をし、
様子の変化を見ていくことが求められます。
戻ってきてすぐは、残業させない、出張させないなどの配慮が必要になりま
す。特に残業は本人も頑張ろうとする気持ちから申し出たりすることがあります。
しかし、そこはいくら本人が出来ると言っても、暫くはさせないことが重要です。
一度再発すると二度三度と再発すると言われます。再発する確率は50%~
70%程度と言われ、二度再発をした人はほぼ一生のお付き合いになると言わ
れています。一度目の復帰をいかにするかにその後がかかっているといっても
過言ではないでしょう。
一人について成功した事例があったとしても、別の人にそれが通用するとは限
りません。ご家族とも連携をとる必要もあります。
個別に復職プランを組み、問題が出てきたのがわかったらすぐに変更するな
ど柔軟な対応が必要となります。
当事務所では提携精神科産業医による、単発の復職時面談、復職後のフォロー面談を可能な仕組みを取り入れています。産業医の選任義務のない事業場、あるいは精神科でない産業医と契約をされている事業場が、必要な時に必要に応じて、精神科産業医の先生にのる面談、相談等していただくことが可能となってます。(料金についてはお問い合わせください。)
会社、人事の方のサポートをしております。
お気軽にお問い合わせください。
厚生労働省HPで
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が改訂されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/index.html
本山社会保険労務士事務所
 03-6427-7751
03-6427-7751