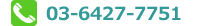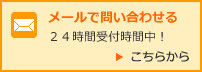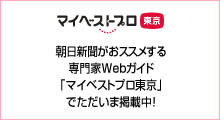健康保険(概略)
【健康保険】
現在、健康保険の仕組みとして以下のものがあります。
1. 社会保険
① 協会けんぽ管掌
② 組合管掌
2. 国民健康保険
(この1.① 1.②、2.は以下においても同じ表記をします)
健康保険はどれに加入するかを選べるものではありません。
1の社会保険は社会保険の適用事業所で雇用され正規社員あるいは正規社員のおおむね4分の3以上の日数、所定労働時間で働く場合、試用期間の有無にかかわらず、採用された日から加入することになります。①か②かはその会社が健康保険組合に加入していれば②に、そうでなければ①となります。
2の国民健康保険は自営業の方や無職の方などが加入することになります。法人の会社ですと1の社会保険に加入しなければなりませんので、法人なのに国民健康保険に加入してくれと言われた場合、本当にそこで働いてもいいのかを考える材料の一つになるかもしれませんので、注意してください。
【保険料・保険料率】
1.① 協会けんぽ
各都道府県の財政により保険料率が決められ、会社のある地域によって違
いがあります。
協会けんぽHP⇒http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
② 組合健保
保険料率はそれぞれの組合で違います。
保険料は会社に入社したとき、固定的賃金が上下し標準報酬月額2等級以上の大きな変
動があった場合、年に一度の算定基礎のいずれかによって、「標準報酬月額」が決定さ
れ、それに基づいて給与から控除されます。標準報酬月額は通勤手当、時間外手当等労
働に対して支給された金額全部が加味されて算定されます。そのためあまり遠くの会社に
勤めると手取りは少ないのに保険料がその割に高くなるということがあります。また月の
どこから入社しても1ヶ月分の保険料が翌月から控除され、退職の時は月末までいるとや
はり1ヶ月分控除されます。
2. 国民健康保険
各市町村で違います。
健康保険料としているところと健康保険税としているところがありす。
保険料を徴収する前者の時効は2年、後者は3年です。
給付や還付の時効が前者は2年、後者は5年と違いがあります。
保険料は前年の所得を基に計算されます。前年はたくさんの所得があったのに今年は
失業中で収入がほとんどないというときなど、かなり保険料がきついと思われるかも
しれません。
【扶養家族】
1.社会保険(①、②)では
生計維持の関係があれば
父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫 弟妹
生計維持要件プラス同一世帯であれば
上記以外の3親等以内の親族(兄姉、伯父伯母、甥姪など)
であって、
世帯が同一の場合年間の収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金を受け
られる程度の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれ
ば、被扶養者となります。対象者の年収は130万円未満だけれど、被保険者の年収
の2分の1以上の場合は、被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況を総合的に判
断して、被保険者の収入が生計の中心と認められれば、被扶養者となります。
同一世帯ではない場合は、年収が130万円未満(60歳以上、障害年金を受けら
れる程度の障害者の場合は180万円)でかつその額が被保険者からの仕送り額より
も少なければ被扶養者となります。
2. 国民健康保険
こちらは被扶養者という概念はありません。世帯人数に応じて金額が決まり、世
帯主に支払い義務が生じます。
【窓口負担】
現在は制度間の窓口負担に違いはありません。
【給 付】
制度による給付の違いは基本的にはありませんが、
社会保険にあって国民健康保険にないものがあります。
「傷病手当金」は健康保険の方にだけあります。
被保険者が病気やけがで会社に出ることができず休みが連続して3日ある場合の4日目
から休んだ日について標準報酬日額の3分の2の額の給付があります。
また、健康保険組合では、財政状態によっては付加金がつく給付があります。
詳しくはそれぞれの組合のHPをご覧ください。
【退職したらどうするの?】
具合が悪くて辞めるなどの場合にはこちらをご覧ください
会社を辞めすぐには別の会社に就職しない場合等、国民健康保険の手続きをしなければ
なりません。病気にかからないからいいやと放っておいて、病気になってから手続きに
行ったとしても、遡って加入ということになり、高額の保険料が徴収されますので気を
付けてください。
また、会社を辞めた後も任意で今まで入っていた社会保険に入る「任意継続」という
仕組みがあります。辞めた後20日以内に自分で手続きを取る必要があります。保険料
は辞めたときの標準報酬月額で計算された金額、あるいは管掌している保険者にいる被
保険者の標準報酬月額の平均で計算された額のどちらかになります。平均より高い給与
だった人は平均の方。それよりも低い給与だった人は自分の辞めたときの標準報酬月額
で計算します。気をつけなければならないのは、会社に勤めていた時は本人負担と同額
を会社が負担していましたが、その分も自分で納める必要があるということです。各市
町村の国民健康保険料(税)の計算方法を調べ、社会保険を継続した方が得か損かを計
算してみることをお勧めします。
 ご不明な点、ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください
ご不明な点、ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください
本山社会保険労務士事務所
 03-6427-7751
03-6427-7751